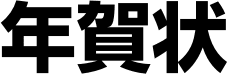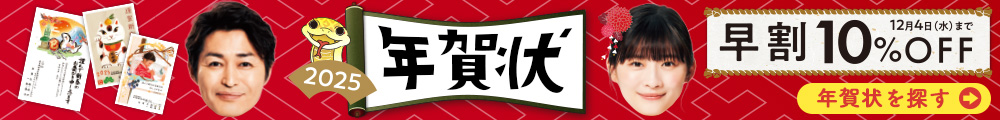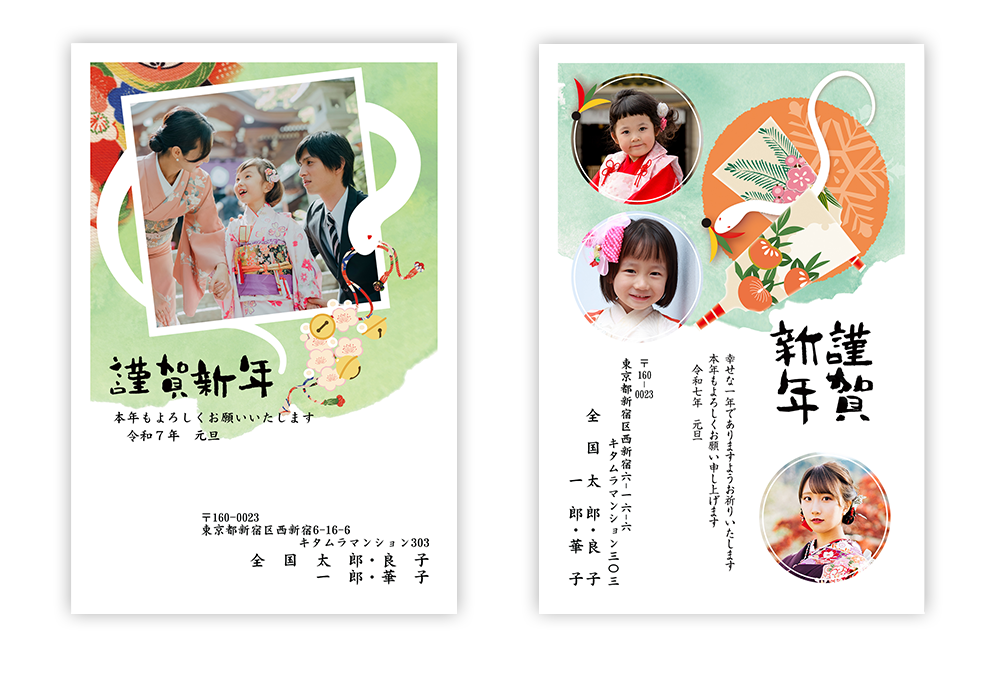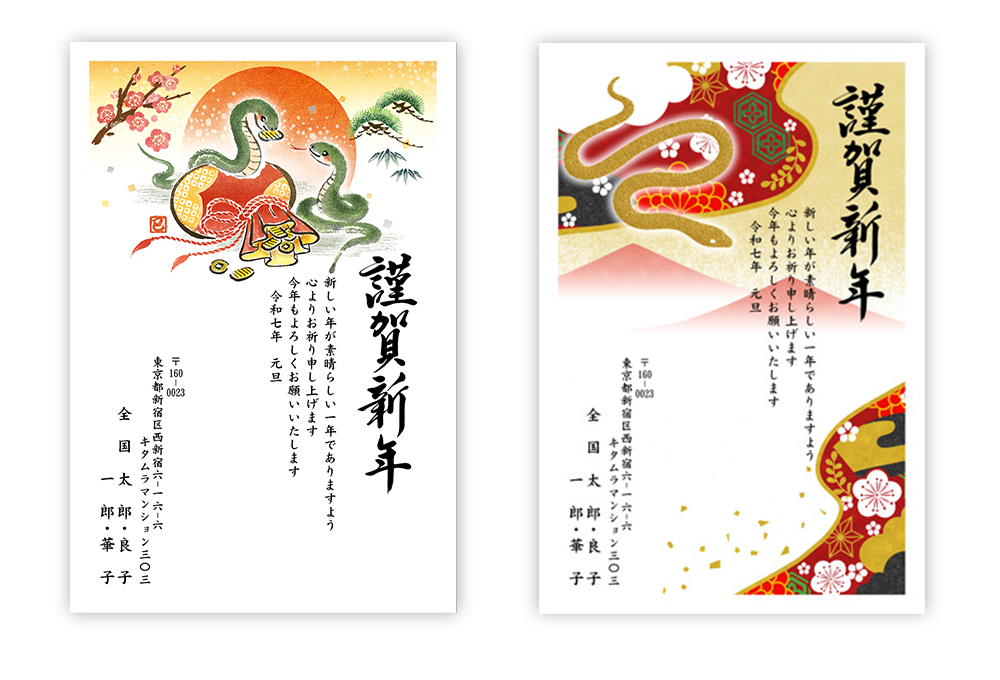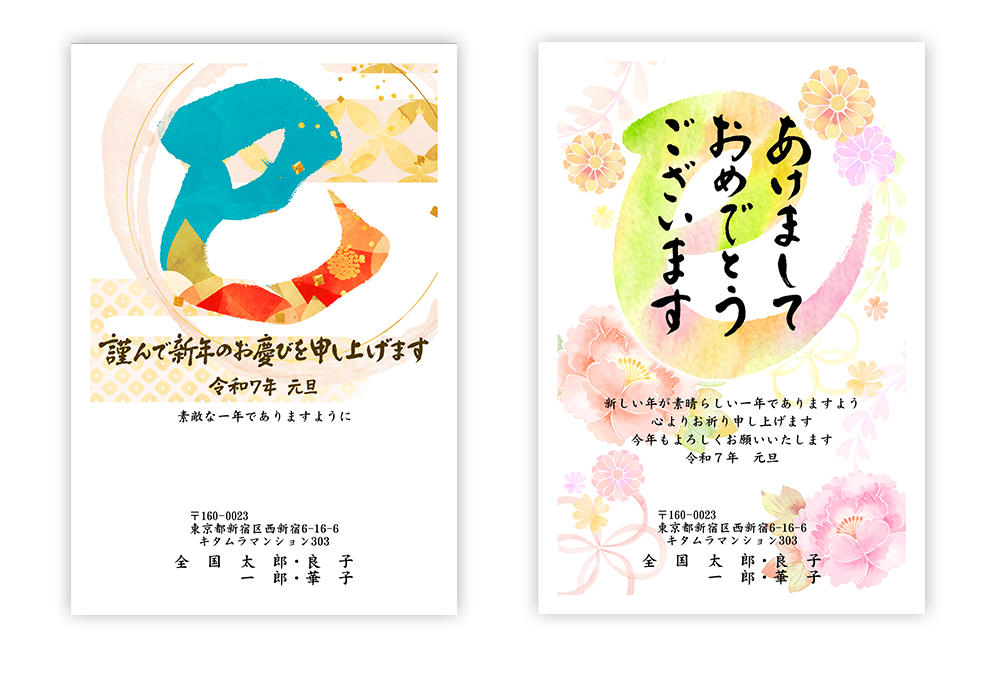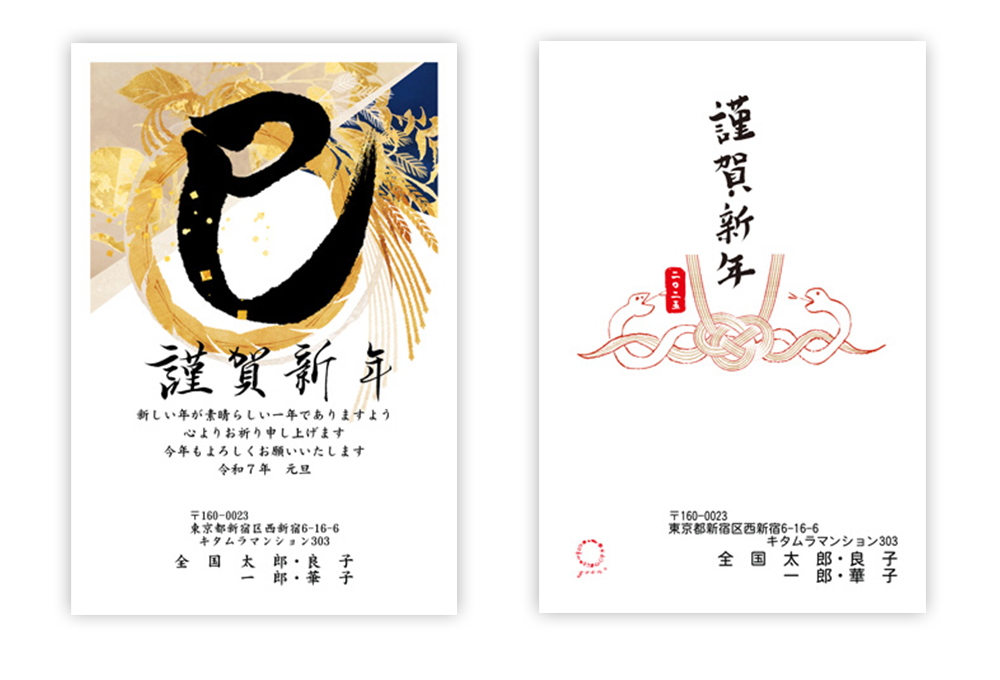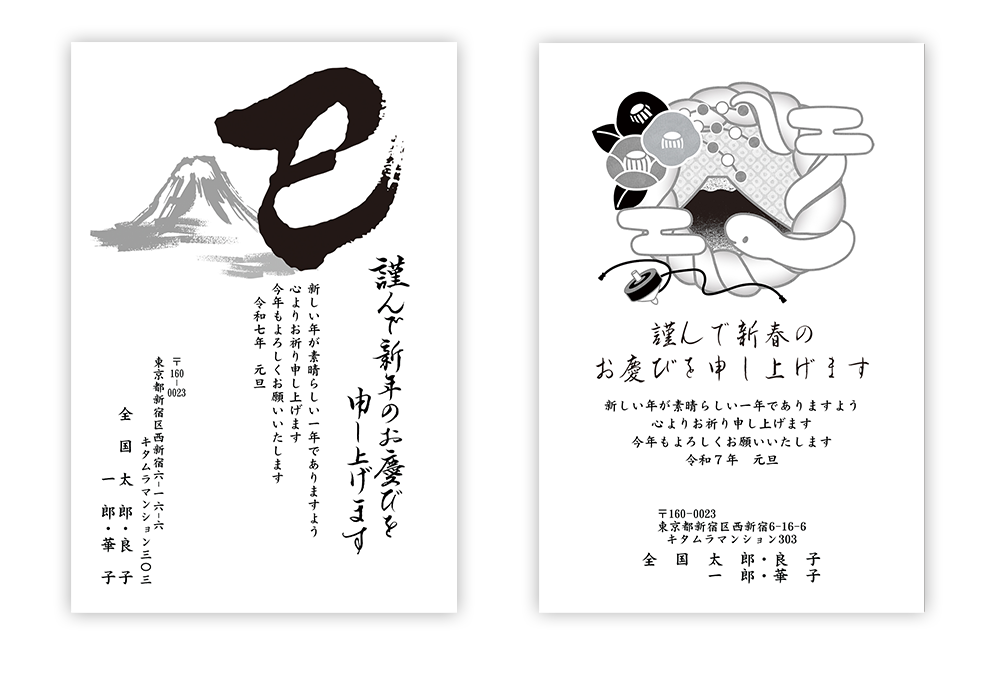喪中の年賀状について、やり取りする相手に失礼がないよう基本的なマナーを知っておきたい方も多いでしょう。この記事では、喪中はがきはどの範囲まで出すか、喪中に年賀状が届いた場合の返事、喪中に年賀状を出してしまった場合の対応などを紹介します。
それぞれの立場やケースごとに、喪中の年賀状に関するマナーを分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
【喪中の方】年賀状は出さない
喪中の方は、年賀状を出さないのがマナー。その代わりに、年賀状のやり取りを遠慮するということを相手に伝えるために、喪中はがきを出す必要があります。
喪中はがきは例年、年賀状のやりとりをしていた方に対して出します。長くやりとりが途絶えている方に出す必要はありません。
一般的に、年賀状の準備をする12月初旬頃までに届くように喪中はがきを出します。
喪中に年賀状を出してしまったらどうする?
喪中はがきに書く内容・書き方はこちら
【喪中はがきを受け取った方】年始状や寒中見舞いで返事を出す
喪中はがきは、「こちらから年始の挨拶をしません」ということを伝えるもの。受け取った側は、喪中はがきを送った側へ年賀状を出しても問題ありませんが、近年では、「喪中はがきを受け取ったら、年賀状は出さない」という対応が一般的になっています。
喪中はがきに「お年始状は遠慮なくお送りください」といった一文が書き添えられている場合は、年賀状ではなく、相手を気遣う言葉とともに年始状や寒中見舞いを出しましょう。
年始状は、「賀」というお祝いの言葉を使わず、「新年の挨拶を申し上げます」といった文面にとどめます。また、年始状よりも寒中見舞いのほうが一般的になっているので、お正月が明けて落ち着いてから、寒中見舞いを送るのもよいでしょう。
年始状や寒中見舞いのほかに、喪中見舞いを出すのも喪中はがきへの返事としての1つの方法です。喪中見舞いは、喪中はがきを受け取ったらなるべく早いタイミングで出すのが望ましいです。早く出すことで、お悔やみの気持ちがより相手に伝わります。
また、喪中見舞いを出す場合は遅くても年内には出すようにしましょう。
そもそも喪中とは?

喪中とは、近親者が亡くなった際、喪に服す期間のことです。故人の死を悼み、悲しみから立ち直るための期間とされています。喪中の期間は1年間で、この期間は年賀状などのお祝い事を原則として行わず、派手な行動は慎むこととされています。
また、忌中とは故人が死後に冥途(めいど)を旅する期間のことで、この期間は亡くなった日を1日目として49日間です。
喪中の範囲はどこまで?
喪に服すべき人は、一般的に亡くなった方から2親等以内の親族とされています。
|
【自分から見たときの喪中の範囲】 ・祖父母 ・父母 ・兄弟姉妹 ・配偶者 ・子供 |
叔父や叔母、従兄弟、甥姪などが亡くなった場合は、喪中にはしない場合が多いです。ただし、亡くなった方との関係性が深い場合、喪中として過ごしても問題ありません。
そのため、兄弟同然として育った従兄弟が亡くなり、お祝いする気持ちになれない場合は、喪中はがきを出すケースもあります。
このように、喪中の範囲には明確な決まりはなく、2親等以内という範囲はあくまでも目安です。2親等以内の方が亡くなった場合でも、同居していない場合は喪中はがきを出さない方もいます。
反対に、3親等以上でも関係性が深ければ喪中はがきを出す場合もあるため、亡くなった方との関係性を基準に喪中とする範囲を決めるとよいでしょう。
喪中の期間はいつまで?
喪中の期間は、2親等以内の親族について最大で12ヵ月から13ヵ月とするのが一般的です。ただし、喪中の期間は親等によって異なります。亡くなった方が1親等(自分や配偶者の父母、子供)の場合、喪中の期間は1年間です。
2親等(自分や配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、祖父母、孫)の場合は、3〜6ヶ月となります。なお、この喪中の期間も目安であり、亡くなった方との関係性によって変わります。
年賀状を出す時期が喪中期間と被る場合に、喪中はがきを出しましょう。
<2025年に喪中はがきを出したほうが良い例>
・2024年1月10日に配偶者の父が亡くなった
・2024年11月20日に自分の祖母が亡くなった
上記の場合は、どちらも2025年の年賀状は出さずに、喪中はがきを出します。逆に、たとえば2024年3月30日に妹の配偶者が亡くなった場合、2025年の年始は喪中期間と被らないため、年賀状を出しても問題ありません。
喪中はがきを出すときのマナー
喪中はがきを出すときのマナーを解説します。マナーを正しく理解した上で喪中はがきを出しましょう。
11月中旬~12月上旬に出す
喪中はがきは11月中旬〜12月上旬の間で、なるべく早く出すのが望ましいです。年賀状の受付は12月15日から開始するため、相手が年賀状の準備を始める前に喪中はがきが届くようにしましょう。相手の都合を考慮して出すのが大切です。
近況報告は書かない
喪中はがきは、年賀欠礼することを伝えるものなので、近況報告などは書きません。結婚や出産、引っ越しなどの近況報告をしたい場合は、喪中はがきとは別に挨拶状や寒中見舞いを出して報告します。
控えめなデザインのはがきを選ぶ
喪中はがきは、華やかなデザインは避けて、控えめなデザインのはがきを使用してください。色を使っても構いませんが、落ち着いたデザインのはがきを選びます。フォントは、明朝体や楷書体、行書体などを使用します。
年賀状を交換している方と葬儀の参列者に出す
喪中はがきを送る相手は、毎年年賀状の交換をしている方と、葬儀に参列してくださった方に出すのがマナーとされています。
また、仕事関係の方には、喪中はがきは出しません。法人には喪中という考え方がないため、仕事関係の方には年賀状を出しても問題ないです。
喪中はがきに書く内容・書き方
喪中はがきは正式には「年賀状欠礼状」と呼ばれます。喪中はがきには、「喪中のため新年のご挨拶ができません」という挨拶文、そして「誰が、いつ、何歳で亡くなったのか」と「故人が生前お世話になったことへのお礼」の内容を書くのが基本です。
故人の年齢は数え年で表記し、その年の誕生日を迎えて亡くなった場合は満年齢にプラス1歳、迎えていない場合はプラス2歳します。
喪中はがきの差出人は、家族の連名でも個人名でも構いませんが、夫婦連名で出す場合、故人の続柄は夫側から見た続柄になります。故人が配偶者の父や母である場合は、差出人と名字が違うこともあるので、フルネームで書くようにしましょう。
書き方は縦書きが基本で句読点は使いません。文字の色は、薄墨と黒どちらで書いてもよいです。宛名面は、黒で書いたほうがよいでしょう。黒で書くことで読みやすく、郵便局の配達員を悩ませません。
喪中はがきに書く内容は以下のとおりです。
|
・年賀欠礼の挨拶 ・故人について ・相手への感謝の言葉 ・結びの挨拶 |
喪中はがきの文例
喪中はがきは形式がほぼ決まっています。なかなか書く機会のない喪中はがきの文章を考えるのは大変ですので、文例を活用しましょう。
<文例1>
喪中のため新年のご挨拶は失礼させていただきます
本年〇月〇日に〇(続柄)〇〇(故人の名前)が〇歳にて永眠いたしました
これまでに賜りましたご厚情を深謝いたしますと共に
明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます
令和〇年〇月〇日
(遺族の住所・名前)
<文例2>
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年〇月〇日に〇(続柄)〇〇(故人の名前)が永眠いたしました
ここに本年中に賜りましたご厚情を深謝いたします
皆様に良き年が訪れますようお祈り申し上げます
令和〇年〇月〇日
(遺族の住所・名前)
<文例3>
喪中のため年頭のご挨拶を失礼させていただきます
かねてより病気療養中でした〇(続柄)〇〇(故人の名前)が〇月〇日に〇歳にて永眠いたしました
本年中に賜りましたご厚情を深謝いたしますと共に
明年の変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます
令和〇年〇月〇日
(遺族の住所・名前)
喪中はがきのさらに詳しい書き方や注意点、状況別の文例はこちら
【状況別】喪中の年賀状や喪中はがきの対応

喪中のときの年賀状や喪中はがきの対応を解説します。喪中の方や喪中はがきを受け取った方、それぞれの対応を確認しましょう。
|
・【喪中の方】親戚や葬儀の参列者に喪中はがきを出す場合 ・【喪中の方】12月後半になって近親者が亡くなった場合 ・【喪中の方】相手も喪中の場合 ・【喪中はがきを受け取った方】喪中の方がいる法人に年賀状を出す場合 ・【喪中はがきを受け取った方】喪中はがきに年賀状を希望する文面があった場合 |
【喪中の方】親戚や葬儀の参列者に喪中はがきを出す場合
すでに喪中であることを知っている親戚や葬儀の参列者であっても、普段年賀状のやりとりがあるのであれば、喪中はがきを出しても問題ありません。
喪中はがきは、逝去を知らせるためのものではなく、年始の挨拶を行わないことを伝えるものだからです。この場合、葬儀への参列のお礼などを書き添えると丁寧になります。
【喪中の方】12月後半になって近親者が亡くなった場合
12月後半に喪中はがきを送っても、先方はすでに年賀状を投函している可能性が高いでしょう。余計な気遣いをさせてしまうため、年末が差し迫っている時期の喪中はがきは送らないほうが賢明です。
喪中はがきを送るのが年末に近くなってしまったら年賀状を出さず、松の内が明けてから、寒中見舞いに喪中であったことを書き添えて送ります。
【喪中の方】相手も喪中の場合
相手が喪中の場合でも、喪中はがきは出します。相手が喪中かどうかは、喪中はがきを出すか出さないかに関係ありません。喪中はがきは、基本的には年賀状を交換しているすべての方に出すようにしましょう。
【喪中はがきを受け取った方】喪中の方がいる法人に年賀状を出す場合
前述したとおり、法人には、基本的に喪中という考え方がありません。代表者などが亡くなった場合でも、取引先等との年賀状のやりとりを行えます。また、年賀状で「賀」といったお祝いの言葉を避ける必要もありません。
ただし、家族経営の会社では、会社と家族が密接な関わりを持っていることから、喪中とすることもあります。この場合は、年賀状ではなく、年始状または寒中見舞いを送るのがよいでしょう。
【喪中はがきを受け取った方】喪中はがきに年賀状を希望する文面があった場合
喪中はがきのお返しとしては、寒中見舞いを送るのが無難です。これは、相手が年賀状を希望している場合も変わりません。
送られてきた喪中はがきに「年始状はご遠慮なく」と書いてあったとしても、年賀状は明るいデザインであることが多いため、寒中見舞いを送るのがよいとされています。
喪中に届いた年賀状には寒中見舞いで返事を!マナーと文例

喪中に届いた年賀状の返信として送りたいのが寒中見舞い。「寒中お見舞い申し上げます」という季節の挨拶の後に、相手の体調や近況などを書くのが一般的な寒中見舞いです。
年賀状にはお祝いを意味する賀詞を書きますが、寒中見舞いは寒い時期のお見舞い状であるため賀詞は書きません。
年賀状の返信として出す場合は、年賀状をいただいたお礼とともに、喪中のために年始の挨拶ができなかったことなどを書き添えるとよいでしょう。
寒中見舞いを送る時期
寒中見舞いは一般的に、松の内が明けた1月8日以降、立春(2月4日頃)までに送ります。配達の期間も考慮し、1月中を目処に投函するようにしてください。
なお、喪中はがきを受け取った方が寒中見舞いを出す場合も、上記と同じ時期に送ります。ただし、喪中はがきへの返信である「喪中見舞い」を出す場合は、喪中はがきが届いた後、すぐに送るのがよいとされています。
喪中に出す寒中見舞いの文例
喪中に出す寒中見舞いの文面は、どのような言葉を使えばよいのでしょうか。喪中はがきを送った相手から年賀状が届いた場合と、喪中はがきを送っていない相手から年賀状が届いた場合、それぞれの寒中見舞いの文例をご紹介します。
<喪中はがきを送った相手から年賀状が届いた場合>
寒中お見舞い申し上げます
寒い日が続いておりますが皆様お元気でお過ごしでしょうか
昨年喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきました
返信が遅くなってしまい申し訳ございません
寒さもますます厳しくなりますが どうかお身体ご自愛ください
本年もよろしくお願い申し上げます
<喪中はがきを送っていない相手からの年賀状が届いた場合>
寒中お見舞い申し上げます
年始のご挨拶を賜りましてありがとうございました
昨年◯月に(故人)が永眠いたしましたので、年始のご挨拶を失礼させていただきました
旧年中にお知らせが行き届かず年を越してしまい誠に失礼いたしました
本年も変わらぬお付き合いのほどよろしくお願いいたします
厳寒の折 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます
寒中見舞いのデザイン
喪中に送る寒中見舞いは、派手なデザインや明るいデザインは避けましょう。松や富士山、日の出といった年賀状に使われることが多いおめでたいモチーフは使いません。もちろん、すでに用意していた年賀状を寒中見舞いに転用することもできません。
寒中見舞いのデザインは、椿のワンポイントが入ったものなど、落ち着いた印象の通常はがきを選びましょう。印刷会社やカメラ店などが販売しているテンプレートの寒中見舞いを利用すると安心です。
喪中に年賀状を出してしまった場合はどうする?
相手の喪中に気づかず、すでに年賀状を出してしまったという場合にはどうしたらよいか迷いますよね。この場合にするべきことを以下にまとめました。喪に服している相手の気持ちを思いやり、次の方法で対処しましょう。
郵便局に取り戻し請求を行う
まずは郵便局に取り戻し請求をかけてみましょう。郵便物の配達前であれば年賀状を回収できる可能性があります。郵便の申し込みにかかった料金は返却されませんが、できるだけ急いで郵便局に相談してみましょう。
お詫びの連絡をする
喪中はがきが届いた時点ですぐにお詫びの連絡をしてください。喪中の方の気持ちに配慮し、「存じあげず、年賀状を出してしまいました。申し訳ありません」と電話でお詫びします。年が明けてから、改めて寒中見舞いなどでお悔やみの気持ちを伝えましょう。
喪中見舞いを送る
喪中見舞いは、喪中はがきを出した相手に対して故人を悼むお手紙のことで、これは喪中はがきを受け取ってからすぐに出すのが通例です。喪中はがきが届いた後、喪中の方に年賀状を出してしまったお詫びと、故人のご冥福を祈る言葉を書いて速やかに送りましょう。
喪中見舞いは、線香やお花などお礼のいらない贈り物を合わせて送るケースも一般的になっています。
寒中見舞いを送る
寒中見舞いは、1月8日から2月初旬頃までに送る挨拶状のことです。1月7日までは「松の内」とよい新年のおめでたい時期にあたるため、1月8日以降に「ご喪服中と存じあげず、新年のご挨拶を申し上げてしまい、大変失礼いたしました」というようなお詫びの言葉、故人のご冥福を祈る言葉を書き送りましょう。
喪中は「喪中はがき」や「寒中見舞い」を出そう
喪中はがきについては、マナーが決められている部分と、故人との関係性によって自分で決める部分があるため、喪中はがきを出す時期や範囲などを把握しておく必要があります。
喪中はがきを出す側・受け取る側のマナーを理解して、相手を不快にさせない行動をとることが大切です。
喪中はがきや、喪中の返信として寒中見舞いを出す際、マナーやルールなどがよくわからないという方も多いでしょう。そんな時はカメラのキタムラにご相談ください。
カメラのキタムラでは、喪中はがきや寒中見舞いの印刷サービスをご提供しております。最短1時間で仕上げられるため、お急ぎの場合でも対応できます。ネットやアプリからでも注文を受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。